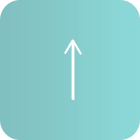婦人科

婦人科

婦人科は、月経の悩みから尿のトラブル、妊娠や不妊に関する相談、子宮、卵巣、乳房の病気や性感染症、更年期障害など、思春期から老年期における女性特有の病気をすべて対象としている診療科です。問診・内診・超音波・子宮がん検診(基本検診)などを通じて、女性がかかりやすい病気の早期発見と治療を行います。女性特有の不調は精神面とも密接に関係していますが、精神的な問題から生じている症状なのかを判断をしてくれるのも婦人科です。女性の身体だけでなく、心にも寄り添いながら診療にあたることも特長といえます。
現代の女性の生き方は多様であり、日常は忙しく、ストレスも多く、本来の女性としての健康を維持できていない方も少なくありません。当院では生活背景も含めて、女性が心身ともに健康な生活を取り戻せるようサポートいたします。生理不順、不正出血、月経前のイライラ、更年期の症状でお困りの方など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
こんな痛みや症状でお困りではないですか?
日常的に起こりやすい症状でも、詳細な検査を行うことで重大な病気の早期発見につながることもよくあります。心配な症状やお困りのことがあれば、一人で悩まず何でもお気軽にご相談ください。
月経困難症とは、生理(月経)の際に強い痛みや不快な症状が現れ、日常生活に支障をきたす状態を指します。これは生理痛の一種ですが、特に症状が重い場合に用いられる言葉です。月経困難症は「原発性」と「続発性」に分けられます。原発性は、特定の病気が原因ではなく、主にホルモンの変動や子宮収縮によるものです。一方、続発性は子宮内膜症や子宮筋腫といった疾患が原因で起こります。症状には、強い腹痛、腰痛、吐き気、頭痛、倦怠感などがあり、特に続発性の場合は病気の治療が必要です。治療法としては鎮痛薬、低用量ピル、ホルモン療法、または原因疾患の治療が用いられます。放置せず、適切な診断と治療を受けることが重要です。
月経前症候群(PMS)は、月経が始まる数日前から現れる身体的・精神的な症状の総称です。原因ははっきりしていませんが、ホルモンバランスの変化や脳内の神経伝達物質の影響が関係していると考えられています。主な症状には、腹痛や腰痛、頭痛、むくみといった身体的なものと、イライラや気分の落ち込み、集中力の低下などの精神的なものがあります。症状の強さや種類は個人差があり、日常生活に支障をきたす場合もあります。このような場合は「月経前不快気分障害(PMDD)」と診断されることもあります。治療法には、生活習慣の見直しやストレス管理、食事改善、薬物療法(ホルモン療法や鎮痛剤など)があります。PMSを軽減するためには、自分の体調を把握し、適切にケアすることが重要です。
過多月経(かたげっけい)とは、月経(生理)の出血量が通常よりも多い状態を指します。通常の月経では出血量が約20〜80ミリリットルですが、過多月経ではこれを大幅に超えることがあります。また、月経が7日以上続く場合も過多月経とされることがあります。過多月経の原因はさまざまで、子宮筋腫や子宮内膜症、ホルモンバランスの乱れなどが挙げられます。また、血液が固まりにくい病気や、特定の薬の副作用が関与していることもあります。症状としては、貧血による疲労感やめまい、日常生活に支障をきたすことが挙げられます。治療には、原因に応じて薬物療法や手術が用いられることがあります。
子宮筋腫(しきゅうきんしゅ)は、子宮の筋肉組織から発生する良性の腫瘍です。女性特有の疾患で、特に30代から50代の女性に多く見られます。筋腫の発生原因は明確ではありませんが、女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)の影響を受けて成長することがわかっています。遺伝的な要因や肥満、初経年齢などもリスク因子とされています。
主な症状には、過多月経や貧血、月経痛、下腹部の圧迫感、不妊、流産のリスク増加などがあります。一方で、小さい筋腫や無症状の場合も多いです。
診断は、超音波検査やMRIで行われます。治療法は、筋腫の大きさ、症状、年齢、将来の妊娠希望などに応じて異なり、薬物療法、子宮筋腫核出術、子宮全摘術、子宮動脈塞栓術(UAE)などが選ばれます。症状が軽度な場合は経過観察が行われることもあります。
子宮内膜症(しきゅうないまくしょう)は、子宮内膜に似た組織が子宮の外側に異常に増殖する病気です。これらの組織は本来、子宮の内側(子宮腔)だけに存在するはずですが、卵巣、腹膜、腸、膀胱などに発生し、月経周期に伴い増殖・剥離・出血を繰り返します。この出血が体外に排出されず、周囲の組織に炎症や癒着を引き起こします。主な症状は、強い月経痛、慢性的な骨盤痛、性交痛、不妊症などです。進行するとチョコレート嚢胞(卵巣内に形成される血液を含む嚢胞)を伴うことがあります。診断には問診、内診、超音波検査、MRI、腹腔鏡検査が用いられます。治療法は、痛みの緩和や病変の抑制を目的とした薬物療法、腹腔鏡下手術などがあり、症状や患者の年齢、妊娠希望に応じて選択されます。
卵巣嚢腫(らんそうのうしゅ)は、卵巣にできる液体を含んだ袋状の構造物です。嚢腫は良性のものがほとんどですが、稀に悪性の可能性もあるため、注意が必要です。卵巣嚢腫は、月経周期に関連して発生することがあり、特に20代から40代の女性に多く見られます。嚢腫の種類はさまざまで、最も一般的なものは機能性嚢腫です。これは卵胞が正常に排卵せず、液体をため込んで膨らんだものです。その他には、チョコレート嚢腫(子宮内膜症に関連)、皮様嚢腫、漿液性嚢腫などがあります。