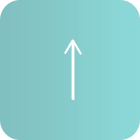産科

産科

産科はお産という視点から、出産に伴う母体の変化、子宮・卵巣など女性性器の異常、さらに子宮内の胎児の状態をみる診療科です。妊婦健診では、体重や血圧の測定、超音波検査、尿検査、感染症検査、血糖値検査、羊水検査などを通じて、母体、胎児ともに問題がないかを定期的に確認します。ときにみられる、妊娠悪阻(にんしんおそ:つわりが悪化した症状)や、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、羊水過多症・過少症といった、妊婦特有の病気にも迅速に対応します。保健指導では辛いつわりへの対処法や生活上の注意点、マタニティーブルーへの対応といった精神面のサポートも行います。
すべての妊婦さんにとってお産は、赤ちゃんを授かったという喜びを感じる一方、身体面や生活面で不安を感じるものです。当院では健康的で、不安なく出産を迎えられるよう、一人ひとりに寄り添った医療でサポートいたします。ご主人とお二人での受診も大歓迎です。ぜひ、お越しください。
生理が遅れたり、軽い吐き気など体調が変化していたり、妊娠検査薬で陽性反応が出たなど、妊娠したかな?と思ったら、ぜひ早いうちにご来院ください。
はじめての診察では、問診と尿検査を行ったうえで内診・超音波検査を行い妊娠の判定をさせていただきます。
胎内の赤ちゃんはめざましく発育し、それに伴いお母さんの身体も大きく変化してきます。妊婦健診では胎児の発育状態を診る超音波検査とともに、妊娠週に応じた様々な検査で、お母さんと赤ちゃんの健康をチェックします。
健診の際は、日常生活や食事のこと、日常での疑問や不安に思うことなど、何でも気軽にご相談ください。
体重測定、血圧測定、超音波検査、尿検査、血液検査、内診、血糖値検査、羊水検査など
妊娠初期は妊娠1~4カ月の時期です(妊娠中期は妊娠5~7カ月、妊娠後期は8~10カ月)。
妊娠初期の症状はおよそ妊娠3~5週あたりで現れ始めます。0~3週では基礎体温の高温層が続いたり、身体のだるさや熱っぽさを感じたりします。4~7週では予定月経が遅れる、乳白色のおりものが多く出るといった症状があります。8~11週では便秘気味になったり、足の付け根がつったりします。腰が重たく感じるようになることもあります。
妊娠初期は赤ちゃんの中枢神経や心臓といった重要な器官が形成されるとても大切な時期です。この時期は葉酸を含む食物の摂取や体を温めることを心がけてください。適度に体を動かし、血流の低下を予防することも大切です。また、避けたほうがよいことは、喫煙、飲酒、カフェインの過剰摂取などです。薬も赤ちゃんへの影響が懸念されるものがあるため注意が必要です。
赤ちゃんがお腹の中で健やかに成長できるように日常生活を送りましょう。
妊娠前には糖尿病と診断されておらず、妊娠中にはじめて発症した糖代謝異常を妊娠糖尿病といいます。お母さんが高血糖であると、お腹の赤ちゃんも高血糖になり、様々な合併症が起こり得ます。お母さんには、妊娠高血圧症候群、羊水量の異常、肩甲難産、網膜症・腎症およびそれらの悪化のリスクがあり、赤ちゃんには、流産、形態異常、巨大児、心臓の肥大、低血糖、多血症、電解質異常、黄疸などのリスクがあります。妊婦さんの7~9%に妊娠糖尿病が認められるといわれています。とくに肥満や糖尿病の家族歴のある方、高年妊娠、巨大児出産既往のある方などはハイリスクとされていますので、必ず検査を受けるようにしてください。
妊娠中に高血圧を発症した場合をいいます。
この病気は、妊婦さん約20人に1人の割合で起こるといわれており、早発型と呼ばれる妊娠34週未満で発症した場合、重症化しやすい傾向があります。重症化すると母子ともに危険な状態になることがある疾患です。妊婦健診をきちんと受診し、適切に周産期管理を行っていきましょう。
早産とは正期産(妊娠37週0日から妊娠41週6日までの出産)より前の出産のことで、日本では妊娠22週0日から妊娠36週6日までの出産を早産と呼びます。早く生まれた赤ちゃんほど、のちに重篤な障害が出てくる可能性が高くなります。ですから、早産にならないように妊娠中は定期的な健診を受けて、早産になりやすい状況の早期診断と予防が重要になります。
切迫早産は早産の一歩手前で、子宮収縮(お腹のはりや痛み)が規則的・頻回に生じ、子宮の出口から赤ちゃんが出てきそうな状態をいいます。切迫早産の治療では、子宮収縮を抑える子宮収縮抑制薬を使用したり、原因の一つである細菌による感染の疑いがあれば、抗菌薬を使用したりすることもあります。
切迫早産や早産の予防のためには、無理のない日常生活を心がけることが最も大切です。妊婦健診をきちんと受診して予防に努めましょう。
マタニティーブルーは、出産後の女性の30~50%が経験するといわれています。産後数日から2週間程度のうちに、涙が止まらない、イライラ、落ち込みといったちょっとした精神症状が出現します。人によっては、情緒不安定、眠れない、集中力がなくなるといった症状も出ることがあります。多くは一過性で、産後10日程度で軽快しますので、過度に心配することはありません。原因としては、急激な女性ホルモン(エストロゲン)低下など内分泌環境の変化に伴って症状が現れると考えられています。ただし、マタニティーブルーの症状が長引く場合は、産後うつ病に移行することがありますので注意が必要です。このような場合はお早めにご相談ください。
超音波検査は高周波の音波を利用して体内を視覚化する検査です。妊婦健診で行う超音波検査(エコー検査)は主に赤ちゃんの推定体重や羊水量、胎盤の位置をチェックします。赤ちゃんの骨格や内臓の状態など身体内部まで観察することができます。4Dエコーは、赤ちゃんの表情や動く様子をリアルタイムに観察することができます。あくびをする瞬間やまばたき、口を動かして羊水を飲んでいる様子なども観察できることもあります。当院の妊婦健診では毎回4Dエコーを実施しています。
出生前検査は、赤ちゃんが持って生まれてくる可能性のある病気を診断する検査で、遺伝学的検査と形態学的検査があります。
母体の血液検査により先天性疾患の確率を推定する検査で、判定できる病気にはダウン症候群、18トリソミー、二分脊椎、無脳症などがあります。血液検査でリスクが少なく受けられる検査ですが、確定診断ではなく、あくまで確率を推定するものです。

中絶手術は、止むを得ない理由があって妊娠を続けられない場合に医療機関で妊娠を中絶することで、正式には人工妊娠中絶と呼ばれています。
中絶手術が可能な時期は母体保護法によって「妊娠22週未満」と定められているため、妊娠21週6日までにしか行うことができません。
妊娠12週から妊娠21週までに行われる中絶を中期中絶といいますが、中期中絶は人工的に陣痛を促すことで赤ちゃんを死産として取り出す方法を用います。
妊娠6〜9週の初期中絶が母体にかかるリスクも最も低く、この時期に手術を行うことが妥当とされています。妊娠10週を過ぎると母体への負担も大きくなってきます。
また、合併症やリスクが高い手術の場合、安全性を考慮し総合病院をご紹介いたします。
当院では、麻酔を使用した子宮に優しいMVA(手動式真空吸引法)にて手術を行います。
次の妊娠に影響が少ないとされている方法です。
当院では、MVA(Manual Vacuum Aspiration)という子宮に優しい手術法を採用しております。
この手術方法は、WHOも推奨する手術法で、子宮のなかにカニューレと呼ばれる柔らかく細いチューブを差し込んで、吸引器で吸い取る方法です。
WHOによって安全性が認められている手法として、電動真空吸引法という方法がありますが、この方法は金属製のチューブを使い電動ポンプで吸引するため、子宮に傷をつけてしまうことや穿孔(突き抜けてしまうこと)を起こすことがあります。
それに比べ、MVAはポリプロピレン製の細く柔らかい管を使用するため、子宮の形に合わせて吸引操作を行うことができます。
また、滅菌された使い捨て器具(ディスポーザブル)を使用し、使用後は破棄するので感染の心配はありません。
MVAは、平成30年4月より流産手術で保険適用となりました。(人工妊娠中絶は保険適応外)
どんな手技にも感染症のリスクがありますが、MVAも例外ではありません。子宮内で細菌が繁殖して感染症を引き起こす可能性があります。術後は感染予防のために抗生剤を処方させていただいております。
術後は1週間程度出血が続きます。通常、少量の出血は自然に治まりますが、大量出血や長期間の出血が続く場合は、追加の処置が必要となることがあります。出血が長引く場合、血腫や出血性ショックの可能性も考慮し、早期に対応する必要があります。
非常に稀なケースですが、吸引時にカニューレが子宮壁を突き破る(子宮穿孔)ことがあります。穿孔が発生すると、手術による修復が必要になることがあります。術後に強い腹痛や発熱を認めた際は直ちに当院へ連絡してください。
MVAで完全に内容物が除去できないことがあります。もし、胎児の組織や異常組織が残っていると、再度手術を行う必要が出てくる場合があります。手技後には、超音波を使って子宮内の状態を確認することが一般的です。
| 期間 | 費用(税込) |
|---|---|
| ~10週 | 143,000円 |
| ~11週6日 | 154,000円 |
| 12週以降 | お問い合わせください |